人生も折り返し付近に差し掛かってくると若いころとは違った悩みが頭をもたげてきますよね。介護なんて問題もミドルエイジにとっては大きな問題の一つです。
それだけでなく教育、収入、自身の老後、いや!まだまだこれからだという気持ちの問題、下手をすると離婚にまつわる問題など枚挙にいとまがありませんよね。
家族だけでなく上司、部下など仕事の悩み、ご近所問題など悩みは尽きないです。
夫婦でも育った環境が違えばおのずと将来の思い描く未来は違って当たり前でしょう。ではどのようにして互いの思いを遂げて行けばいいでしょうか?
結論:夫婦どちらかの目が曇れば崖に向かって進んでいるのも気付かない時があります。解決には時間がかかるのが常です。慌てずに一番の理解者である妻には本心をさらけてみるべきと考えます。いずれ夫婦ともども老いる事は決まっています。それならばじっくりと準備のために互いの家族も巻き込んで修羅場になろうともじっくり進めてみるべきと思います。夫婦なのですから。
- 互いの親の健康状態
- 互いの親が考える今後への思い
- ミドルエイジたちの思いや考えを親世代は知っているのか?
- 場所や時間、距離、するべき作業量など介護までに知る状況把握
- ミドルエイジたちの子供や自身への思いをすり合わせているか?
- 将来の理想像を共有できているか?

悩みの要約
相談者:52歳男性。子供の小学校入学を機に、田舎へ引っ越したいと考えている。
相談内容:
- 両親の介護や相続の問題があり、田舎へ引っ越したい。
- 妻に相談したところ、猛反対された。
- 妻は、現在の住まいで幼稚園のママ友と良好な関係を築いており、引っ越したくないと考えている。
- 妻は人見知りで、新しい環境に馴染むのが苦手。
- 妻の母親は、東京に出てきて一緒に住みたいと言っている。
相談者の心情:
- 両親のことが心配で、近くにいたい。
- 田舎暮らしは、子供にとっても良い環境だと考えている。
- 妻を説得したいが、理由が分からないため困っている。
回答者(弁護士)のアドバイス:
- 妻にとって、田舎は全く知らない土地であり、不安が大きい。
- 妻の母親は、東京に出てきたいと言っており、妻の気持ちと矛盾する。
- 相談者の両親も、東京に出てくることを検討してはどうか。
- 妻の気持ちを尊重し、引っ越し以外の方法で両親をサポートすることを検討すべき。
- 夫婦でよく話し合い、お互いが納得できる解決策を見つけることが大切。
MCからのアドバイス:
- 相談者のプランは、一人よがりになっている可能性がある。
- 10年後、妻が不満を抱え続ける可能性が高い。
- 家族の形は一つではない。
- 必ずしも一緒に住む必要はなく、良好な関係を保つ方法もある。
- 妻が新しい人間関係を築くのが苦手な場合、特に配慮が必要。
結論:
相談者は、妻の気持ちを尊重し、引っ越し以外の方法で両親をサポートすることを検討すべき。
テレフォン人生相談
引用元
 回答者
回答者両親の介護と相続に関する事をする為に田舎に帰りたいが妻に大反対されているので何とかできないかという相談ですね。



そうですね。妻は田舎では暮らしたくないのは、ちょっと人見知りな性格で子供のお母さんたちとコミュニティが確立されているので原因にはそういった理由があるかもしれないです。



確かに奥さんの気持ちもわかりますが、もう少し教えて下さい。あなたのご両親の状態を教えてもらえますか?



えっとですね、今介護が必要かと言われれば今はそうではありませんが、3年後ぐらいには非常に厳しいのではないかなと。今は私が月一回雑用を済ませています。もともと、賃貸業等で相続などいろいろと問題があって元気なうちに筋道をつけたいというのが私の希望です。



あぁそうですか。なるほど。あなたはご両親の資産管理とまぁ面倒を見たいと。では奥さんの方にも親御さんがいると思いますが?



そうですね。妻の親は母親一人で同じ県内の田舎で暮らしています。うちの親と同年代ですがいずれ東京に出て孫娘と一緒に住みたいと言っているようです。



そうですか。あなたにとっては故郷でなじみがありますが奥さんにとっては全く見ず知らずですね。そこは根本的な違いですね。それと奥さんにとっては東京で住みたい理由がある。ではあなたの方でもご両親を説得して都会に住むという理屈もありますよね。理屈で言えばどっちだってあるよね。



そうですがうちの親は先祖代々の墓や土地、親戚もあって離れられないと言いますか、もし一人になれば考えてくれるかもしれないですが今は離れるつもりはないですね。



奥様にとっては天地がひっくり返るようなお話だよね。環境が全く変わるんだから。奥様を説得するという事を出発点にするなら絶対にまとまらないのはあなた自身が分かっていますよね。あなたがご両親の事を思っているのはすごくわかるんですけどもう少しフラットになる必要がありますね。奥様とはこれから数十年と一緒にお子様を育てなきゃいけないですよね。そこで今回の事で生じた亀裂はなかなか回復できませんよ。そのうえで親をどう見ていくか視野に入れるべきでは?あなたの描いているプランでは一人で先走っていると思います。



あの先生、無理やりというわけではなく話し合いで・・・



もうすでに亀裂は入っています。今の状態で説得しても間違いなく深まります。このまま進めて10年後を考えると奥様は毎日不満です。ご主人もフラットに考えてお互いの状況も踏まえて説得でなく亀裂を埋めるコミュニケーションをとる努力をしてみてはいかがでしょうかというのが私の回答になります。



ありがとうございます。もう少しフラットに考えます。失礼します。
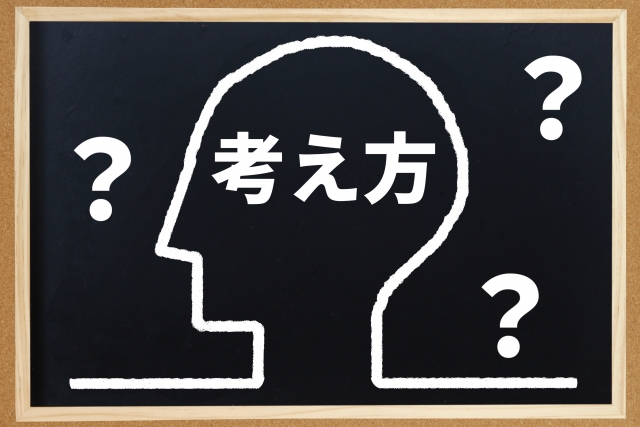
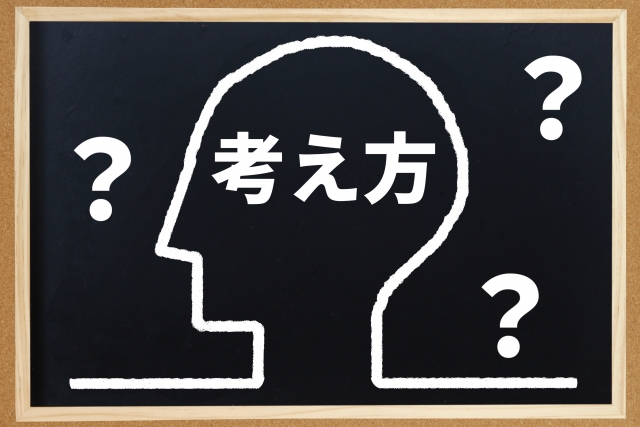
【介護にまつわる尽きない悩みとは】ミドルエイジの親への思いとは?!
ちょうど50歳代ミドルエイジに待ち受ける介護の入り口でした。今回は心配のあまり先走ってしまったことが大切にしないといけない妻との亀裂につながりました。
特に大黒柱と世間では言われる世帯主にとってはこういった話はもっと頭に浮かんできますよね。仕事はどうすればいい?子供の学校は?妻にはいつ言うべきか?賛成してくれるか?もしかすると俺が何とかしないといけない?
いや俺が何とかしないといけないんだ!よし!俺が解決してやる!な~んて一足飛びに結論を急いでませんか?
又はあの人は全く何も考えていない!どうするのよ、子供の学校は?お金も潤沢にないのに!なんで自分で考えて行動してくれないのよ!私の親の話でもないのに!私は嫌よ、あの人の親の介護なんて!とふわ~っと思い浮かんでませんか?
でも多かれ少なかれ、あなたの親もおじいちゃん、おばあちゃんも何世代にもわたって繰り返されてきました。あなただけがそんな事にはならないと考える方が統計的に見ておかしいですよね。


親は老いるもの。あなたも子供の頃から親の背中を見ていたはず。
人間誰でも老いるものですよね。なら僕たちがするべき事は何でしょうか?まずは知る事ではないでしょうか。でもこのブログを見ているミドルエイジの皆さんはもうわかっているので割愛しましょう。
では具体的に知るって何でしょうか?介護保険でしょうか?施設等の知識を深める事でしょうか?僕は親の体調や認識に変わった事がないかなぁと知る事だと思います。
- 車や車庫など傷やへこみなど新しいものが増えていないか確認してみる。
- 感情の起伏が激しくなっている。又は逆に何を言っても生返事など生気に陰りが見える。
- 服や身なりに乱れに感じるようなものを見受けられる。
- 冷蔵庫の中のものがぐちゃぐちゃだったり同じものであふれている。
- トイレや浴室などの汚れを気にかけない。
- 手の届く範囲に物があふれて消費期限が切れていたり惣菜などが無造作に置かれている。
- よく見るはずのカレンダーを何時までもめくらない。など


もう保護者でなく扶養者になったのだ!
分かっているんです。もう責任のある大人だって。でも親が老いるのは信じられないですよね。僕が小さい時にはよく拳骨を落とされたものです。
父親は怖くて、いや、母親も怖かったです。掃除機を壊したと言って学校から帰るなりいきなり「こらー!!、あんたやろ!こんなことしたの!!」と言われました。
たしかに僕が壊しました。
そんな事を思い出すと元気で頼れる親がそこにいてるようです。でも本当は違います。あなたが扶養するべき人がそこにいます。
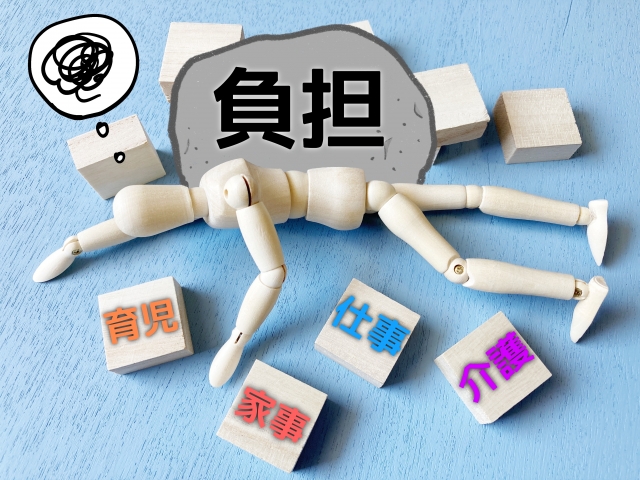
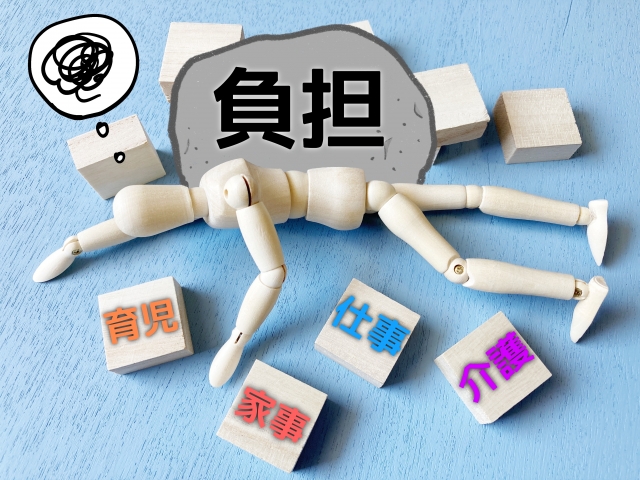
親は本当は面倒をかけたくないと思っている?!
俺の親だから「自分の事はいいから子供の事をしてね。」と言うはずだ。"俺の親の限って"認知症にはなるはずがない。介護が必要になるはずがない。と一字違えば馬鹿親と呼ばれることも子供から見ると親への思いもそのように勝手に勘違いしているかもしれません。
でも、親も人生の荒波を乗り越えてきました。介護や教育、仕事、いろんな付き合い、ストレス、自身の病気、家族の病気など様々なり超えてきました。
精神力もすり減ってきています。実は助けて欲しいと思っていて丁度いいかもしれませんね。親は大事な存在と思っているあなたには出来る事は出来るだけ心身ともに健康であって欲しいと思います。
僕たちミドルエイジが健康であり続ければ親もストレスが少なくなるはずです。


まとめ~尽きない悩み【親への思い編】
子は親を、親は子を扶養する義務があります。法律にもそのように明記されています。確かにそうでない親子もおります。
確かに法に触れるからと言って罰則があるわけではなく、自治体などでも対応してくれる場合もあります。
でも親にも忸怩たる思いをもって荒波を乗り越えてきました。子は子で次の世代を育てる責務があるので現在乗り越え中であります。
ミドルエイジたる僕たちがどちらにも義務があるなら前もって準備しておきましょうよ。
いずれその思いが子に伝わり、親にも伝わり、自分に反映される時が来ると思います。僕たちも少しずつ老後に向けて一歩ずつ進んでいるなら前向きに明るく進みましょう。







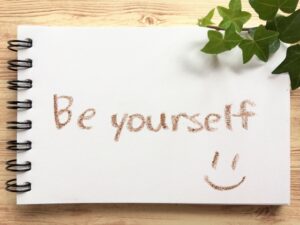



コメント